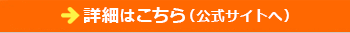<今回のポイント>
1.先週の米国株式市場は調整した
2.マーケットは「地固め」する必要がある
3.雇用統計では平均時給に注目
4.ブラード総裁の警鐘に注目
5.利上げは、かならずしもドル高を意味しない
6.インフレ圧力があるなら素材、エネルギー、工業、市況株を買え
米国株式市場は調整局面へ
今週金曜日の雇用統計に注目
先週の米国株式市場は、ダウ工業株価平均指数とナスダック総合指数が週間ベースで-0.5%、S&P500指数が-0.7%でした。これで週間ベースの連続上昇記録は4週間でストップしたことになります。
これまで上げピッチが急であったこと、この水準からは上値抵抗が意識されること、などから、もう一段高するためには、まずここらへんでコンソリデーション、つまり「地固め」する必要を感じます。

今週の重要イベントは、言うまでもなく4月1日(金曜日)に予定されている雇用統計の発表です。
3月の非農業部門雇用者数のコンセンサス予想は20万8000人です。

同じく失業率のコンセンサス予想は4.9%です。

でも今回の雇用統計のデータの中で最も注目されるべき数字は平均時給だと思います。ちなみに2月はこの数字が-3¢(下のグラフ中、黄色の2月の部分に注目して下さい)で、これは予想外に弱い数字でした。

この弱い平均時給が引き金となって、先の連邦公開市場委員会(FOMC)で示されたドットプロット(FRBメンバーによる今後のフェデラルファンズ・レートの平均値)は、2016年末の時点で、これまでの1.4%から0.9%へと大幅に下がりました。

これは今年中の利上げ回数がこれまでの4回から一気に2回へ半減することを示唆する数値です。
インフレの心配が死んだわけではない
市場のインフレ期待は上昇している
ただインフレの心配が全然無くなってしまったのか? といえば、それはそうとも限りません。
前回のFOMCではイエレン議長が「アネクドート(裏話)としては、賃金上昇プレッシャーがある例は、たくさん、耳に入っている。いかんせん、データを見る限り、それが平均時給に反映されていない」と、ドットプロットを下げて来なければいけなかった事情を、未練たっぷりに語っていました。
実は平均時給のデータ収集はちょうど月の真ん中あたりが締切りとなっており、2月22日から実施となったウォルマートの賃上げは、それに捕捉されていないという指摘もあります。
このことから、一見弱々しく見える賃金が、意外なほど急激に切り返してくる可能性も無いとは言えないのです。
賃金以外のインフレも、頭をもたげています。
下のグラフは5年先5年物期待インフレ率のチャートで、これは米国財務省証券とTIPS(物価連動)債の利回りの差から求められ、市場のインフレ期待を表わしています。

それによると市場のインフレ期待は、スルスルと上昇していることがわかります。これは、このところの原油価格の反発などに呼応した動きだと思われます。
マーケットに影響力を持つ
「風見鶏」のブラード総裁が釘を刺す意味
先週、セントルイス連銀のブラード総裁が「4月26・27日に予定されている次のFOMCは捨て駒ではない」と発言しました。
一般に市場参加者は(FRBが利上げするのは記者会見が予定されているFOMCに限る)という先入観を持っています。
4月のFOMCは記者会見が予定されていないため、(今回は利上げはパスされるだろう)というのが強いコンセンサスになっています。
ブラード総裁は、その時の状況に応じて、タカ派になったり、ハト派になったり、風見鶏(かざみどり)のように意見を変えることで知られています。そのタイミングが絶妙なので、マーケットに対する神通力を誰よりも持っています。
その意味では、今回の雇用統計で、強い平均時給の数字が出てくるリスクに備えておく必要があると私は考えます。
インフレとはお金の価値が下がること
「インフレ気味の国の通貨は売られやすい」ことを知っておく
そこで投資ストラテジーですが、皆さんに覚えておいてほしい概念は「インフレ気味の国の通貨は、売られやすい」ということです。
普通、「利上げは通貨高要因だ」と早飲み込みするトレーダーが多いです。たしかに金利差という面では利上げ国の金利は魅力が増すので、それは一見すると通貨高要因のように錯覚しがちです。
しかし利上げしても通貨高にならない、情けないほど弱い通貨を持つ国のエピソードには、枚挙にいとまがありません。もし利上げが自動的に通貨高を意味するのなら、なぜブラジル・レアルやロシア・ルーブルはだらしなく下がっているのでしょうか?
それはそれらの国にはインフレ圧力があるからです。
皆さんの中には(インフレとは、物価が上がることだ)と勘違いしている人が多いですが、それはそうではありません。インフレとは、お金の価値が薄まっていることを指します。
お金の価値が目減りしているから、前よりも沢山の金額を払わなければ、昔と等価の財やサービスを手に入れることが出来ないのです!
さて、今後米国で利上げの議論が再燃した場合、それはドル高に直結するか? といえば、それはそうとも限らないということを私は主張したいのです。
ブラジルやロシアのように、利上げしても通貨高にならない国は、掃いて捨てるほどあります。
むしろインフレのリスクに対して、フェデラルファンズ・レートの水準が「後手に回っている」かどうか? の判断の方がはるかに重要です。
利上げということになると、株式は一旦、調整するでしょう。その後、出直りが早いのは、インフレの環境下でアウトパフォームしやすいセクター、具体的には素材、エネルギー、工業、市況株ということになります。
【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】
⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月1日時点】
「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
|
【SBI証券のおすすめポイント】 |
|
| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |
|
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |
|
| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |
|
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |
|
| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |
|
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |
|
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
|
| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |
| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |
|
| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |
|
| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |