大塚家具
関連するキーワード
三陽商会 デサント ワールド しまむら ファーストリテイリング 吉野家ホールディングス ワタミ ロイヤルホールディングス リンガーハット 日本マクドナルドホールディングス コロワイド 鳥貴族 高島屋 松屋フーズ イオン ローソン ファミリーマート 良品計画 コスモス薬品 セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス ペッパーフードサービス ZOZO 三越伊勢丹ホールディングス マツキヨココカラ&カンパニー 大創産業 日立製作所 東芝 三菱電機 安川電機 パナソニック セイコーエプソン NEC 富士通 キヤノン リコー キーエンス ローム 京セラ 村田製作所 ルネサスエレクトロニクス 富士ゼロックス 森ビル レオパレス21 三井不動産 三菱地所 住友不動産 野村不動産ホールディングス オープンハウス 日産自動車 トヨタ自動車 マツダ ホンダ スズキ SUBARU ヤマハ発動機 デンソー 現代自動車(ヒュンダイ) ワークマン ジャパンディスプレイ ヤマダ電機関連特集
関連ニュース
第4回
辞任する大塚家具の久美子社長と未熟なコンサルに見られる「共通項」とは
中野豊明
大塚家具の大塚久美子社長が辞任を発表した。過去の業績について、経営責任を明確にすることが理由のようだ。コンサルティング業界に長く身を置いた筆者から見ると、その経営アプローチは、未熟な若いコンサルのやり方と重なって見えてしまう。

#12
7大業界「コロナ後の世界」をコンサル脳で総予測!生存戦略を一気読み
ダイヤモンド編集部,杉本りうこ
コロナ禍で社会と産業は激変した。勝ちモデルは消失、退場待ったなしの企業が続出している。経営戦略に精通した外資コンサルの資料を基に、慢性的な病理からビジネスチャンスまでが分かる図表を各業界1枚ずつにまとめた。

予告編
アパレル・外食・小売り…主要7業種の「生存戦略」を外資コンサル4社が解明
ダイヤモンド編集部
コロナ禍で社会と産業は激変した。これまでの勝ちパターンは消失、コロナ前からもうかっていなかった企業は退場待ったなしだ。あらゆる業界と企業が悩むアフターコロナの生き残り戦略を、外資コンサルが総力で解明する。

#17
資金繰り危険度ランキング、「継続企業注記銘柄」の中でも苦しいのは?
ダイヤモンド編集部,鈴木崇久
新型コロナウイルスの感染拡大が企業業績に与えるインパクトについては、まだ不透明な部分が大きい。そこで、コロナショック前から監査法人が「事業の継続が疑わしい」と判断していた42社を対象に、「資金繰り危険度」ランキングを作成した。
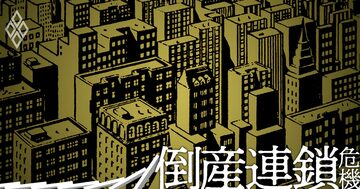
ヤマダ電機が大塚家具を子会社化した理由、販路拡大だけではない?
金子浩明
ヤマダ電機が業績不振に陥っている他業種の大塚家具を傘下に入れる狙いはどこにあるのでしょうか。ヤマダ電機の狙いについて、アンゾフの「成長マトリクス」と「シナジー効果」を用いて解説します。

大塚家具はヤマダ電機傘下で本当に再建できるか、甚だ疑問の理由
真壁昭夫
12月12日、家具・インテリアの小売りを手掛ける大塚家具が、家電量販大手ヤマダ電機との資本提携契約を締結すると発表した。これにより大塚家具はヤマダ電機の子会社となる。大塚家具は自力での再建をあきらめ、ヤマダ電機傘下での経営再建を目指す。

ヤマダ電機が大塚家具を子会社化、40億円超で第三者割当増資を引き受けへ
ダイヤモンド編集部,布施太郎
経営再建中の大塚家具が、ヤマダ電機の傘下に入る決断をしました。自主再建を断念し、ヤマダ電機の子会社になることで経営再建を果たす考えです。

大塚家具が3月末で手元資金枯渇も、新スポンサー確保が生命線
ダイヤモンド編集部,布施太郎
「大塚家具の先行きは、かなり怪しくなってきた」──。企業再生を長く手掛けてきたある銀行の審査担当役員はこう分析する。

Part4
ソニー社長が目標を利益ではなく「キャッシュフロー」にしたワケとは!?
ダイヤモンド編集部
企業のニュースの実例を読むことで、楽しく決算書の読解術が身に付く「決算書100本ノック!」特集(全4回)の4回目。商社、ソニー、大塚家具、ドン・キホーテなどを題材にしています。
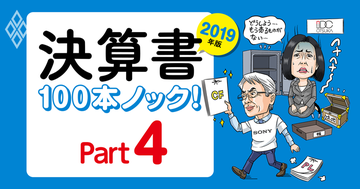
大塚家具、業績回復と父娘和解が不可能ではないと言える3つの視点
鈴木貴博
お家騒動で親子関係が断絶し、業績悪化に悩む大塚家具の大塚久美子社長。先日、父・勝久氏を訪ねて「業界団体のトップへの就任」を提案したが、和解できずに終わった。大塚家具はこれからどうなってしまうのか。実は、見方によっては環境は良い方向へ向かっていると言える。

大塚家具が土壇場で38億円調達、複雑な増資スキームの裏事情
ダイヤモンド・オンライン編集部,週刊ダイヤモンド編集部
経営再建中の大塚家具が、第三者割当増資で38億円を調達する財務増強策を公表した。複数の取引先や米系ファンドが絡む複雑な増資スキームの背景には、中国を舞台にした関係者のさまざまな思惑が交錯する。
