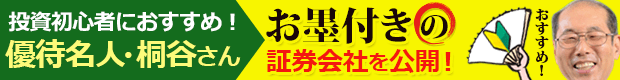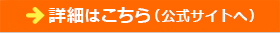独身者のマネープランを考える特集も最終回。今回は「独身者の家について」。買ってしまうほうがいいのか、賃貸のほうがいいのか? 独身でいると、家についてなかなか真剣に考えるタイミングがやってこないが、金額的には大きいものであるだけに無計画でいると後か怖い。一度しっかり考えてみよう。
【参考記事】
●”一生結婚しないかもしれない”リスクに備える!
~独身が考えるべき「一生のお金」(1)~
●「年収400万円・独身」が”老後も逃げ切れる”マネープランとは?
~独身者が考えるべき「一生のお金」(2)~
●老後のために、独身のあなたが毎月貯蓄しなければいけない金額は?
~独身者が考えるべき「一生のお金」(3)~
独身者も"自分の家"について考えよう
一般的に、人生で「マイホーム」を考えるのは、結婚して家庭を持ったときだろう。だが、独身者にとっては、そのマイホームを真剣に考えるタイミングがなかなかやってこない。そのまま何も考えずにいると、「あのときなら住宅ローンを組めたはずなのに」とか「若いうちから老後に払う家賃のために貯蓄しておくべきだったのに」などと後悔しかねないので、独身者であってもマイホームについてきちんと考えてみるのは大事なことだ。
家を買おうとしている人や、実際買った人は、よく「賃貸の家賃を払い続けているのがもったいないから」という言葉を口にする。だが、近頃は"家を買うお金と、生涯賃貸暮らしで支払う家賃の総額には、(両者が同じくらいのスペックの家なら)それほど差がない"という説も一般的になってきた。
ということは、持ち家と賃貸、どちらでもいいということなのかもしれないが、実際はどちらにもメリットとデメリットがあるはず。そしてそれは、ファミリーと独身者とでは意味合いが変わってくるだろう。はたして独身者にとって、本当にメリットのある"家"とはどんなものなのだろうか。
持ち家なら、老後に毎月出ていく住居費の心配をしなくていい
近年、一人暮らし用のマンションを購入する独身者が増えているという。「その傾向は、特に女性に強いようです」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの山崎俊輔さんだ。
「そもそも、家が買えるくらい計画的に貯めているのは、女性のほうが多いんですね。もちろん、男性でもマンションを買う人は結構いますが、それは自宅としてではなく、投資用だったりするケースもままあります。
いずれにしても、独身者が家を買うのは、一口にいいとも悪いともいえません。持ち家は資産ともいえますが、条件次第では重荷にもなってしまうこともあるからです」
それではまず、独身者にとっての持ち家のメリットとは何なのか? 山崎さんはこう話す。
「家を買って、リタイアまでに住宅ローンを完済していれば、収入が限られている老後の生活の中で、住居費が管理費や固定資産税だけにとどまり、賃貸暮らしの場合よりも格段に少なくなります。その点が持ち家の最大のメリットでしょう。これは独身に限らず、ファミリーでも同じです。
また、独り身にとって"終のすみか"の存在は、心のよりどころにもなります。『頼るパートナーや子どもがいなくても、家さえあれば何とかなる』と思っている人は多いのではないでしょうか。たしかに、頼る人もおらず、持ち家もなく老後資金も乏しいというのは最悪の状況なので、現役時代に家を買っておくのは、最終的に持ち家と賃貸のどちらのほうが金額的にトクか、ということではなく、一つの"安心を買っておくこと"でもあります。
公的年金水準は、家賃を織り込んでいないと考えるのが適当です。”これだけ持ち家政策を講じてきたのだから、国民は家を定年までに確保しているはず、年金は日常生活費をまかなう水準で設定しよう”と国は考えてきたからでしょう。その意味でも『終のすみか』を定年までに確保する必要が出てきます。
もし、老後も賃貸暮らしだと、たとえ家賃5万円の部屋でも、年間の支出は60万円。ということは、老後が20~30年あるとすると、住居費だけでおよそ1000~2000万円は飛んでいく計算になります。しかも、これは家賃5万円の部屋に住む場合の金額で抑え目。もう少しいいところに……と思うと、さらに膨れ上がります。その分を現役時代から準備できればもちろん問題ないですが、この準備をするには、"かなり高い計画性"が求められるでしょう」(同)
高すぎる物件を買うと、自分の首を絞めることになる
それでは、逆に持ち家のデメリットとは何なのか? 同じくファイナンシャルプランナーの江原さとみさんは、次のように指摘してくれた。
「家は、資産に余裕がある人が現金一括で買うならいいですが、そうでない場合は住宅ローンを組むことになります。が、原則として独身の方が借金を背負うことはあまりおすすめできません。夫婦の場合は稼ぎ口が2人いるので、もし夫が病気になっても妻が働いて何とかできるかもしれませんが、独身者はそうはいかないからです。
それに、一般的な収入の独身者であれば、買っていい物件の価格は、準備できる頭金にもよりますが、2000万円以下が目安になるでしょう。それ以上だと返済がきつくなり、リタイアまでに完済できなかったり、老後に向けた貯蓄が思うようにできなくなりがちです。が、モデルルームに見学に行き、思わず予算よりも高すぎる物件を買ってしまう人が少なくありません」
高すぎる家を買ってしまうと、そのしわ寄せが老後生活に来てしまうということだ。
「また、少しでも結婚の可能性がある人も、家を買わないほうがいいでしょう。単身者向けのマンションを買い、その後しばらくして急に結婚することになった場合、手狭になった部屋を"売る"もしくは"貸す"ことを考えるでしょうが、どちらもかなり難しいからです。
まず、単身者向けのマンションは、資産価値があまり高くない――つまり、それほどニーズがないため、よほどいい物件でなければ転売が難しいのが特徴です。貸すにしても、希望通りの金額で貸せるとは限りません。実際、賃貸収入よりもローン返済のほうが高くついて、毎月赤字になっているケースは山ほどあります。
上級者であれば、売ったり貸したりする可能性も視野に物件を選ぶのでしょうが、なかなか普通の人にはそこまで見定められません。そのため、無理せず、迷ったら買わないという選択肢が無難といえるのです」(同)
そのほかにも、ファイナンシャルプランナーの八ツ井慶子さんによれば、副産物として次のようなデメリットも。
「賃貸より持ち家のほうが、スペックの高い住居になる可能性が高いので、必然的に光熱費が上がる傾向にあるようです。
また、私は仕事で個人のマネー相談を受けていますが、家を買った人は往々にして、家具・調度品に散財しがち。普段は10万単位、100万単位などのお金は当然慎重に使うのに、数千万円の家という大きな買い物をした余波で、金銭感覚が狂うのかもしれません。そこで数十万円を軽い気持ちで使ってしまうと、取り戻すには相当なパワーが必要です。退職金の一部でローンを完済するはずが、家やそれに付随するものにお金を使いすぎたために退職金が全部消える羽目になったケースも見たことがあります」
若い頃の住まいに、年を取ってからも住みたいかどうかはわからない
一方の賃貸暮らしにも、もちろんメリットとデメリットはある。それは、いずれも持ち家のケースの裏返しだ。
まず、メリットは借金を背負わないので身軽であること。逆にデメリットは、老後の住居費を心配しなければならないことが大きい。山崎さんは言う。
「先ほど、持ち家が重荷になることがある……といいましたが、年齢を重ねると、若い頃に住んでいた家に住みづらくなる可能性は大いにあります。たとえば、会社に通いやすいから、と都心に買った高層のマンション。老後に住むには環境として厳しいかもしれませんよね。どこか別の場所に引っ越したいと考えても、マンションが売れなければ身動きが取れない場合もあるでしょう。その点、賃貸ならば、そのつど自分の状況に合わせて住まいを変えられます」
今の世の中、年を取って一人暮らしだと、家を借りにくいという風潮があるものの、八ツ井さんは「2035年には3人に1人が高齢者の時代。不動産賃貸業者も、そんなことをいっていたら店子を集められませんから、状況は改善されているはず」と話す。
「それに、賃貸暮らしが特に向いている人もいます。1つ目のタイプは、実家をもらえる予定の人。家を買う必然性がないので、賃貸暮らしで老後資金や、実家を引き継いだときのリフォーム代などを貯めていけばいいでしょう。
2つ目のタイプは、勤め先から家賃補助を受け、家賃を安く抑えられている人。こういうケースは、この制度をなるべく長く利用しない手はありません。買ってしまえば家賃補助は受けられないですから、制度を利用できる限り賃貸で暮らして、老後のためにできるだけお金を貯めておくのが理想的です」(同前)
現役の間に賃貸暮らしをして、着実に貯蓄ができていれば、「定年間際に現金一括で(もちろん老後資金分の蓄えは残した上で)家を買うのもOK」とは、八ツ井さん、山崎さん、江原さんの共通見解。
「身動きが取れにくくなるデメリットはあっても、やっぱり老後の賃貸住居費を計画的に準備するのは大変だし、老後になってから毎月少なくないお金を支払うことへのストレスもあるはず。それを思うと、あくまで"身の丈にあった範囲"で、"リタイアまでに完済"するという条件を満たせば、どこかに終のすみかを用意するのもいいと思います」(山崎さん)
独身者にとっての持ち家、賃貸のメリット、デメリットはおわかりいただけただろうか。
これを踏まえて自分がどうするべきかを考える際は、家族(親・兄弟など)と話し合うことも重要だろう。親がいっしょに住みたいと考えていることもあるかもしれないし、実家を相続する場合は、兄弟と話し合う必要があるかもしれないからだ。
その上で、買うなら"自分が余裕を持って買える物件の価格"を検討し、あらかじめ返済計画を立て、現役のうちにローンは必ず払い終える。賃貸で行くなら、老後の住居費を貯めることを念頭に、貯蓄が今のままで十分かどうか見直す――などの準備を始めていこう。
「住宅ローンの返済期間などを考えると、45歳くらいまでには買うか賃貸かを決めておくのがベターです」(八ツ井さん)。
独身だから大変なわけではない。大切なのは”準備をしておくこと”
これまで、4回にわたり独身者のマネープランについてみてきた。ここで確認しておきたいのは、「独身者はファミリーより大変」というわけではないということ。仮に”同じ年収で生きていくならば”、独身者よりファミリー世帯のほうがお金が掛かる。単純に独身者であることがデメリットというわけではない。
ただ、独身者は「家計が苦しい」という切羽詰った状況に陥りにくいため、ファミリーに比べて使い方や備える意識が希薄になりがち。また、稼ぎ口が1つしかないため収入を増やす手段が限られている。1人だからこそ、きちんと考えられる人は"自分しかいない"ことを肝に銘じて、一度、自分が生涯生きていくためのお金のについて考えてみることが大切なのだ。
それによって、「今までのようにお金を使っているのは危ないかも」「もっと計画的に貯めていかないと……」等、今後のお金の使い方、貯め方に対する意識が変わってくるかもしれない。
住居費の面から実家を譲り受けることが必要ならば、家をもらう代わりに親の面倒は自分がみるなど、親や兄弟と一度きちんと話し合ってみたり、家族と助け合える関係を築いておくことも重要になる。
さらには、年収を考えて「いまの仕事のままでいいのか」「キャリアアップのために今、自分は何をしなければいけないか」と働き方に向き合ったり、あるいは「やはり1人で生きるのは大変だから、結婚をきちんと考えてみよう」という気になるかもしれない。とかく女性が「生活(お金)のために結婚する」と言われがちだが、もはや男性も同じで、豊かに生きるための手段として結婚を考えることがおかしくない時代になったのではないだろうか。
自分の一生のお金について考えることで、自分の生き方そのものが変わってくるかもしれないのだ。
(取材・文/元山夏香)
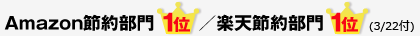
『約7000世帯の家計診断でわかった! ずっと手取り20万円台でも毎月貯金していける一家の家計の「支出の割合」』
大人気の家計再生コンサルタント・横山光昭さんが7000人の家計診断して「手取り20万円台の一家が、無理・ムダなく毎月貯金できる、家計の"支出の割合"」を大公開!
何にいくら使っていいのか、配分・金額が一目瞭然。低収入に怯え、やみくもに節約する生活から解放されること、間違いなし!

★Amazonはこちら!(Amazonに再入荷しました!)
★楽天ブックスはこちら!(楽天に再入荷しました!)
★丸善ジュンク堂はこちら!
★7ネットはこちら!
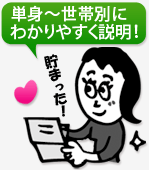
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
| 【2026年2月5日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |
||||||
| 株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||
| 1約定ごと | 1日定額 | |||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2639本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
| 【SBI証券のおすすめポイント】 口座数では業界トップクラスの大手ネット証券で、最大の魅力のひとつは国内株式の売買手数料が完全無料なこと。取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で9年連続1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
| ◆三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1853本 | ○ 米国 |
|
| 【三菱UFJ eスマート証券のおすすめポイント】 MUFGグループの一員であり、さらにau経済圏と連携するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査<金融業界編>」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ |
||||||
| ▼【ザイ限定】2000円プレゼントの特典情報も掲載!▼ | ||||||
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1936本 | ○ 米国 |
|
| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。HDI-Japan主催の「HDI格付けベンチマーク」2025年証券業界では、「問合せ窓口」「Webサポート」2部門で3年連続「三つ星」を獲得。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1860本 | ○ 米国、中国 |
|
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 2024年1月からNTTドコモと業務提携を開始。「dカード」でのクレカ積立、dカード年間利用額特典による投信購入など、ドコモとの提携サービスが続々登場している。日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、約5100銘柄の米国株や2700銘柄以上の中国株を売買できる。「dカード」「マネックスカード」などの提携クレカで投資信託を積み立てると最大3.1%のポイント還元。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ! ポイント還元率は最大3.1%とトップクラスで、「dカード PLATINUM」ならお得な特典も満載! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆【マネックス証券NISA「つみたて投資枠」のメリットは?】積立対象の投資信託が264本もあり、初心者も安心の資産設計アドバイスツールが使える! |
||||||
| ▼クイズに回答+口座開設で2000円分のポイントがもらえる!▼ | ||||||
| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 665本 | ○ 米国 |
||||
| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国で設立され、グローバルに展開しているネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は約6300銘柄と大手ネット証券を圧倒。米国株の売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(上限は22米ドルで他社と同水準)。さらにリアルタイム為替なら為替手数料が無料なので、米国株の売買コストを抑えたい人にはおすすめ。米国株の情報も充実しており、米国株投資にチャレンジしたい人には、魅力的な証券会社と言える。また、日本株の売買手数料が完全無料なので、日本株を売買したい人にもおすすめ。取引アプリに搭載された対話型AIの「moomoo AI」も便利。株の基礎知識から市場動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、投資初心者には力強い味方となる。また、多くの先輩投資家たちが書き込みを行う投資掲示板は、株初心者にとって役立つ情報源となるだろう。NISA口座も利用可能。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! 為替手数料無料&約6000銘柄を24時間取引可能で、AIツールも使える“低コスト&充実のサービス”を解説 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |
||||||
| ▼入金5万円以上で「最大10万円相当の人気株」が当たるキャンペーン実施中!▼ | ||||||
| ◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 55本 | - | |
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料(0円)なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |
||||||
| ▼積極的に売買する短期トレーダーに人気!▼ | ||||||
| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 2610本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード(一般カード/ゴールド/プレミアム/ブラック)で決済すると0.5〜2%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2600本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※電話注文を除く |
163本 | ○ (CFD) |
||||
| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 従来から売買手数料の安さがウリだったが、2025年9月からネット取引の場合、国内株式(現物・信用取引)と投資信託の売買手数料が完全無料に! コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の金利については、大手ネット証券よりも低く設定されており、一般信用売りも可能だ! 米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。国内店頭CFDについては、2024年度まで11年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |
||||||
| 【関連記事】 ◆【GMOクリック証券の特徴とメリットを徹底解説!】日本株の売買手数料が無料のうえ、米国株から金まで世界中の商品を売買できるCFDや高機能アプリが魅力 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! |
||||||
| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||
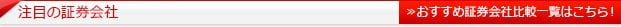
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設+条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら

| お得な限定キャンペーン! | クレカ積立がお得 | 株の売買手数料がお得! |
|---|---|---|
|
SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |
三菱UFJ eスマート証券 取引ツール「kabuステーション」が機能充実! |
松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |
| ザイ・オンラインで人気NO.1の大手ネット証券!⇒関連記事 | 「三菱UFJカード」などでクレカ積立がお得!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |