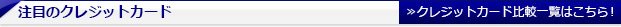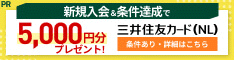新年はモチベーションがアップしやすいタイミング
節約をするなら「固定費」の見直しから手を付けよう
2019年も残すところあとわずか。よくお話ししていることですが、新年を迎えるタイミングは、何か新しいことを始める好機です。これまで、今一つ節約や貯蓄に身が入らなかった人も、2020年から気持ちを切り替えて、自分の家計と向き合ってみてはいかがでしょうか。
年初には、まず「今年のお金の目標」を設定するのがおすすめです。「今年こそ1年で100万円貯める」といった具合に、貯蓄の目標額を具体的に決めるほか、「気になっていたけど、手を付けられていなかった『iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)』や『つみたてNISA』『ふるさと納税』を始める」などもいいですね。
「iDeCo」や「つみたてNISA」「ふるさと納税」は、仕組みを理解して取り組めば、どれも間違いなく役に立ち、得することもできる制度です。ただ、始める前の段階で、少なからず情報収集が必要になるため、「いいとは聞くけど、なかなか始められないでいる」といった声も耳にしがち。新年こそ、このハードルを乗り越えたいところです。
【※関連記事はこちら!】
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
⇒iDeCoを始める前に知っておきたい4つのメリットを紹介! 入金時・運用時・出金時に優遇される「3段階の節税効果」に加え、金融機関や商品を選べるのも魅力
⇒ふるさと納税の仕組みと始め方をわかりやすく解説!自己負担額たった2000円だけで返礼品をもらう方法や通信販売並みに便利に使いこなすワザを一挙紹介!
もっと貯蓄を増やしたいという場合には、必然的に節約が必要になるでしょう。手軽に始められることといえば、「コンビニでお菓子を買うのをやめる」「コーヒーをしょっちゅうテイクアウトするのをやめる」などでしょうか。こうした、何気ない浪費をストップすることも、もちろん効果的なのですが、せっかく新年に一念発起して取り組むのであれば、もう少し“手間のかかる節約”にもチャレンジしてみましょう。
手間のかかる節約といえば、やっぱり「固定費の見直し」が挙げられます。固定費とは、毎月ほぼ定額の出費が発生する費目のこと。住居費、通信費、保険料、教育費、車の関係費用(駐車場代、ガソリン代など)あたりが該当します。水道光熱費も、月ごとに多少の変動はあるものですが、固定費の一種と見なしてもよさそうです。
また、最近はサブスクリプション(定額制)のサービスが流行し、動画配信サービスを皮切りに、さまざまなサブスクリプションのサービスを利用する人が増えています。月額数百~数千円程度と、比較的少額のサービスが多いせいか、複数のサブスクリプションのサービスを利用し、結果的に少なくない出費になってしまっている例も多いもの。これらも、見直すべき固定費と言えるでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒流行りの定額制 “サブスクリプション” の賢い使い方を伝授! カラオケ、ラーメン、弁当などの飲食系や、ワイシャツ、花、家電、家など注目サービスを紹介!
固定費は、ちょっとコンビニでのムダ遣いを控えるのとは違い、解約手続きやサービスの乗り換え手続きなどの手間が生じる分、見直しのハードルは高くなっています。ただし、その分だけ、見直した後も節約効果はずっと続くので、節約をするのであれば、固定費から手をつけるのが鉄則です。
そこで、ここからは私がおすすめしたい、固定費の節約テクニックをいくつか紹介していきましょう。
住居費・通信費は見直し効果が大きい費目!
化粧品はトライアルを活用するなど、工夫して節約を!
【住居費の見直し】
固定費の中で、最も負担が大きいものの一つが「住居費」です。「住宅ローンの月々の返済額が高すぎる」「賃貸だが、家賃が負担でお金がなかなか貯まらない」――どちらも非常によく聞く悩みです。
そもそも、月々の手取り金額から考えて、明らかに高すぎる物件を買ったり、借りたりしないことが先決なのですが、だからといって、すぐさま引っ越すのも難しい場合も多いかもしれません。そんなときに、挑戦したいのは「住宅ローンの借り換え」。賃貸派の人なら「家賃交渉」です。
持ち家で住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローンを最初に契約した状態から見直さない人が多いですが、別の住宅ローンに借り換えると、返済総額を減らせることはよくあります。あくまで目安ですが、ローン期間が10年以上、借入残高が1000万円以上残っており、借り換え前後の金利差が1%以上ある場合は、手数料を加味しても、借り換えたほうが得する可能性が高いでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒【住宅ローン借り換えランキング】住宅ローン金利(18銀行・500商品)を比較して、お得なローンを探そう!住宅ローンのプロが、変動・固定の金利推移を解説!【2019年12月最新版】
賃貸の場合は、大家さんに交渉することで、家賃を下げられる場合があります。人気物件や人気エリアだと難易度は高くなりますが、住んでいる建物にいくつか空室があるような場合、家賃交渉に挑む価値は大いにあります。一般的に、大家さん側としても、店子に出て行かれるよりは、多少値引きしてでも定着してもらったほうがいいと考えるものだからです。
家賃交渉は更新のタイミングで行うのがセオリーですが、引っ越しが多い時期(3月、4月など)よりも、引っ越しが減ってくる時期(5~7月など)にトライしたほうが、うまくいきやすい傾向にあるようです。
家賃交渉が難しく、引っ越しを考える場合には、家賃に注目するのはもちろんですが、それに加えて、“家賃をクレジットカード払いにできる物件”を選ぶのもおすすめです。以前は、家賃というと口座引き落としや振り込みで支払うのが一般的でした。しかし、最近では、家賃や諸費用をクレジットカード払いにできる物件や不動産会社が増えています。
家賃をクレジットカード払いにできれば、ポイントやマイルを貯められるので、結果的にその分だけ家賃が割引されているようなものです。ただし、物件によっては利用できるクレジットカードが決まっている場合も。また、クレジットカードによっては、家賃がポイント付与の対象外だったり、仲介手数料はOKでも家賃が対象外だったりすることもあるので、必ず事前に確認したほうがいいでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2022年の最優秀カード”を詳しく解説!
【通信費の見直し】
スマホの通話・パケット通信料と端末代の分割払いで、月額1万円前後か、それ以上の出費を強いられている人も多いはずです。あまりにも高額な携帯電話料金の値下げを促すために、政府は2019年の秋から「改正電気通信事業法」を施行。これにより、大手の携帯電話会社が行っていた通信料と端末代の「セット販売」(一定期間、通信契約を結ぶことを条件に、スマホなどの端末代を値引きする販売手法)が禁じられることになりました。
セット販売の問題点は、端末を頻繁に買い換えない人だと、通信料が不当に高くつきやすいという点にありました。今後は通信料と端末代が分離されるため、携帯電話会社以外のショップ(家電量販店など)で安い端末を購入し、自分に合った通信プランを選択することも容易になります。また、通信料を値引きする代わりに、中途解約で高額な違約金を課すシステムも禁じられることになっています。
改正電気通信事業法の影響で、NTTドコモ、au、ソフトバンクといった大手携帯電話会社の通話・パケット通信料は、値下げ傾向になっています。とはいえ、さらに通信費を下げたいのであれば、「格安スマホ」も有力な選択肢です。
格安スマホとは、その名のとおり、料金の安いスマホ業者のこと。なぜ料金が安いかといえば、自社で通信回線を持たず、NTTドコモ、au、ソフトバンクの通信回線をレンタルして、サービスを提供しているからです。
格安スマホにすると、月額使用料を1500~2500円程度まで引き下げることも難しくありません(端末代を除く)。大手キャリアの3分の1~4分の1程度の料金に収まるイメージです。しかも、大手キャリアから乗り換えた場合に、それまで持っていた端末をそのまま使い続けられるので、使用感に大きな変化はなく、料金だけ引き下げることが可能です。
とはいえ、スマホで長時間の通話をすることが多い人や、常に最新の端末を持っていたい人には、格安スマホは不向きです。格安スマホは大手キャリアのスマホと異なり、オプション料金を支払わないと、無料で通話し放題にならない場合がほとんど。身内や友人との長電話であれば、Lineの無料通話などを利用することでカバーできますが、ビジネスで頻繁に通話するのであれば、大手キャリアを選んだほうが無難でしょう。
逆に、通話は少なく、パケット通信がメインの人には、格安スマホが最適です。ただし、格安スマホ会社は大手キャリアの通信回線をレンタルしていることから、通信回線が混雑しやすいランチタイムや帰宅時間帯などは、通信速度が遅くなる傾向にあることも、覚えておいてください。
【保険料の見直し】
医療保険や死亡保障の生命保険、自動車保険に火災保険、年金保険など、複数の保険に加入している人は多いでしょう。住宅ローンと同じで、加入したらそのまま放置しているパターンが多いですが、保険は毎年新しい商品が発売されているので、定期的に見直しを行い、必要に応じて入れ替える必要があります。
基本的に、新しい商品のほうが、内容的により行き届いたものに刷新されている場合が多いもの。火災保険のように、昔と今とで、保険の基本的な構造さえも、大きく変わっているものもあります。
10年以上前だと、火災保険といえば「時価」で契約するのが普通でした。この場合、たとえ焼失して建て替えることになっても、焼失時点の建物の経年劣化を加味した分しか保険金が出ません。しかし、現在は火災で焼失する前の建物と同等のものを新たに建てられるだけの保険金が受け取れる、「再調達価額」の契約の保険が主流です。
新築から何十年も経った家で「時価」の火災保険に入っている場合、実際に火事にあって建て替えが必要になっても、必要十分な保険金が受け取れない可能性が高いため、「再調達価額」の契約に切り替えたほうが無難です。しかし、保険の見直しという発想がないと、そのまま放置してしまい、いざというときに困る可能性が高いのです。
また、最近は台風の影響で風水害が話題になっていますが、古い火災保険の場合、風水害に対応する特約を付けていないケースもしばしば。逆に、どんな特約に加入しているかがわからず、請求漏れをするケースも多く、これだと保険料のムダ払いになってしまいます。
医療の保険も大きく変わってきています。たとえば、自費診療で高額になりやすい先進医療については、医療保険に特約で付加するのが当たり前でしたが、現在は単体の先進医療保険も登場。「貯蓄と健康保険の保障でカバーできるから、医療保険は不要だけど、先進医療保険には備えたい」という人は、先進医療保険だけに加入することで、保険料を抑えられるようになったのです。
このように、保険業界はどんどん変化しているので、大きなライフイベントがあったときはもちろん、何もなくても、5年に1回程度は保険の見直しをしましょう。
なお、保険料を少しでも節約するには、クレジットカード払いにするのがおすすめ。保険会社によって対応は異なりますが、一般的にインターネットから契約できる保険会社の多くは、クレジットカード払いが可能なことが多くなっています。
また、保険料を月払いではなく、年払いにして1年分をまとめて支払うと、月払いのときよりも保険料が2~3%安くなることがあるので、検討してみてください。
【その他の費目の見直し】
ここまで、家計の中で大きな割合を占めがちな固定費を3種類取り上げてきました。ここからは、その他の費目の節約ワザを紹介します。
 エネチェンジは電力会社やガス会社の料金比較ができるサイト。
エネチェンジは電力会社やガス会社の料金比較ができるサイト。拡大画像表示
まず、電気代やガス代ですが、現在は自由化が進み、まったく異業種の企業が電気やガスを販売できるようになっています。といっても、電気やガスを作り、供給するのは元の電力会社やガス会社なので、販売会社を変更しても、電気やガスの供給に問題が生じる恐れはありません。
ただ、かなり多くの会社が電気・ガスの販売に参入してきているので、取捨選択が難しいところ。比較検討が重要なので、簡単なシミュレーションで自分に合った会社を探すことができる「エネチェンジ」などのサイトを活用するといいでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒電気代を一年間で約4万円も節約する節約術を公開! LED電球、白熱電球、蛍光灯それぞれの電気使用量と価格、寿命を比較して、確実に電気代を節約しよう!
次に、個人的に固定費の一種だと考えているのが、化粧水などの基礎化粧品です。最近は、女性だけでなく男性でも使用している人が多いと思いますが、価格帯がピンキリなので、高価なものを定期的に買っていると、出費が平気で年間数万~10万円以上にも及んでしまいます。
基本的には、お手頃価格のものを普段使いしたいものですが、たまには高級なものを使いたい、ということもあるでしょう。そんなときにおすすめなのが、トライアルセットを活用することです。
多くの化粧品メーカーでは、一週間や10日分などのトライアルセットを販売しています。普通に買うと1万円以上する基礎化粧品のセットが、1000円以下で試せたりもするので、さまざまなブランドのトライアルセットをお試ししてみるのもよさそうです。
最後にサブスクリプションのサービスについて。契約するときは絶対に使うと思っていて、実際に始めたばかりのときは物珍しさもあり、頻繁に活用していたとしても、だんだん使わなくなるというケースはありがち。飲食系のサブスクリプションなどは、ある程度の期間は利用しても、だんだん味に飽きてくるというケースも多そうです。使わないものは整理する、以外の節約ワザはないのですが、まずは見て見ぬふりをやめるところからトライしましょう。
契約は簡単でも解約は面倒で先延ばしにしがちなものですが、年末年始のお休みのタイミングなどで、じっくりと家計の棚卸しをしてみてはいかがでしょうか。
(取材/元山夏香)
【※関連記事はこちら!】
⇒定期預金の金利が高い銀行ランキング![2020年・夏]金利がメガバンクの100倍の「あおぞら銀行」など、「夏のボーナス」は高金利でお得な銀行に預けよう!
⇒【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2022年の最優秀カード”を詳しく解説!
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月16日時点・最新情報】
|
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード(NL) |
||||
| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |
||||
◆JCB CARD W(ダブル) |
||||
| 1.0~10.5% (※1) |
永年無料 | JCB | QUICPay |
 |
| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |
||||
◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
||||
| 0.3~1.5% (※1) |
3万9600円 | AMEX | - |
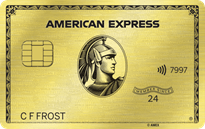 |
| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |
||||
| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード ゴールド(NL) |
||||
|
0.5~7.0% |
5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |
VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |
||||
◆三菱UFJカード |
||||
| 0.5~7.0% (※1) |
永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
- |
 |
| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |
||||
◆楽天カード |
||||
| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |
 |
| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |
||||
| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |
||||