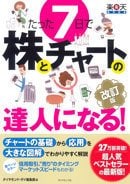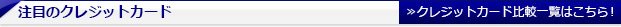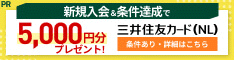景気や企業業績の動きはトレンドやサイクルをなす習性があり、それを反映して動く株価もトレンドやサイクルをなす習性があります。ですから、株価チャートを見ていくときには、まずトレンドを意識すること、そして、その背景にあるファンダメンタルズの動きを考えることが大事であり、それこそが株価チャートを実践的に使いこなす最大のコツ、というのが前回の結論でした。
では、株価トレンドが上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、横ばいトレンドなのか、それはどう判断したらいいのでしょうか。そのための切り札として移動平均線の使い方のコツを紹介していきましょう。
移動平均線に注目していれば、リーマンショックは避けられた
移動平均線については後ほど基本からお話するとして、まずは実例から見ていきましょう。
下の株価チャートを見てください。これは、2005年から2007年にかけての日経平均の週足チャートです。この時は小泉政権、そして第一次安倍政権と連なる時期で、改革期待と世界的な好景気の流れの中で順調な株価上昇が続いていました。
 【図1】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
【図1】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
このチャートに描かれている補助線は52週移動平均線というものです。過去52週間(約1年間)の株価の平均値を連ねたものですが、日経平均はこの線に沿って順調な上昇トレンドを描いていることがわかります。そして、株価がこの線の近辺まで来ると反発しやすく、良い買いポイントになっていることもわかります。
ところが、Bの局面で株価は52週移動平均線をハッキリと割り込んでしまいました。それまでも少しだけ割り込むことはありましたが、これだけズドンという感じで割り込むのはこの上昇トレンドの中では初めてでした。
実は、この下落から日経平均は下降トレンドに転換して、その後1年近くに渡って株価が下がり、翌年の10月にはリーマンショックにより6000円台まで行きました。上の図のB地点から半値以下の水準まで下がってしまったわけです。
ここで注目したいのは、A地点とB地点はよく似たような動きにもかかわらずB地点の下落が決定的に重要なサインになったということです。結果的にもそういうことがいえるわけですが、テクニカル的には52週移動平均線を割り込んだかどうかで、その重要度の違いがその時点でも判断できました。
ここで大切なことは、B地点で、「いままで相場のサポート線として強力に機能していた52週移動平均線を、どうしてこんなにも割り込んでしまったのか」を真面目に考えることでした。
この当時、アメリカで低所得者向けの住宅ローンであるサブプライムローンが大量に発行されていたのですが、それがだいぶ焦げ付いてきて問題視され始めていました。当時は「サブプライムローン問題」と言われて騒がれ始めていました。
この問題については、当時、専門家の間でも「アメリカの住宅部門の中でもごく一部のセクターの問題だから、日本経済にはあまり影響がないだろう」という意見が大半でした。しかし、日経平均が52週移動平均線を大きく割り込む動きを見て、「これは、何か大変なことが起きているのかもしれない」と警戒を強めることができたのではないかと思います。
移動平均線は第一に「向き」、第二に「位置」で判断する
そこで、今度は移動平均線について基本からおさらいしてみたいと思います。
まず、移動平均というのは、一定の期間の終わり値の平均値です。そして、それを連ねた線が移動平均線です。
たとえば、5日移動平均というのはその日を含めて過去5日間の終値の平均値です。それを連ねたものが5日移動平均線です。式で表すと、
5日移動平均=過去5日間の終値の合計÷5
となります。
株価は上昇か横ばいか下落のいずれかのトレンドをたどっているケースが多いのですが、毎日の値動きを見ていると上がったり下がったりしているので、そのトレンドが分からなくなりがちです。
そこで、毎日の上下動に惑わされずに株価の大まかな方向性を探るために移動平均線を使うわけです。一定期間の平均値を連ねた移動平均線は短期的な動きに大きく左右されずにゆったりと大まかな方向性を描いていくからです。
移動平均線の見方としては、第一に線の向きが大切です。線の向きそのものがトレンドを示すと考えられるからです。
第二に、線に対する株価の位置が大切です。上昇トレンドの時には、線が上向きで株価がその上に乗る形で上昇を続けますが、株価が線を割り込んだらトレンド転換の兆しとなる可能性があります。
線が上向きの状態で株価が線を割り込んだ時には、線の向きの方を重視して上昇トレンドと判断しますが、
・線を大きく割り込む
・線を割り込んだままなかなか回復しない
という場合には、トレンド転換の可能性が高くなり、線が下向きに転じたら「トレンド転換した」と判断します。
株の買いポイントは、
・株価が線を突破して線が上向いたところ、
・線が上向きの時に、株価がその線近辺まで下落してきたところ
の2つです。売りポイントはこの逆になります。

また、移動平均線はさまざまな期間のものが描けますが、その利用の目安は以下の通りです。株価トレンドといっても、短期的なトレンドから長期的なトレンドまで様々ですが、短期的なトレンドを捉えて短期売買する場合には短期の移動平均線、長期的な投資をするなら長期の移動平均線を利用するのが基本です。
・5日移動平均線……数日程度の短期売買
・25日移動平均線……数日から数週間程度の短期売買
・13週移動平均線……数週間から数カ月程度の投資
・26週移動平均線……数カ月から1年程度の投資
・52週移動平均線……半年~2年程度の投資
・120カ月移動平均線……優良株の数年に一度の投資チャンスを探る
株式投資で儲けやすい時期と儲けづらい時期の判断
日経平均は過去の動きを見る限り平均3~4年程度のサイクルで上下動しています。これは、戦後の日本の景気サイクルが平均4年程度であることと関係していると思われます。
そして、この平均3~4年程度のサイクルを捉えるには、過去の事例を見る限り52週移動平均線または12カ月移動平均線が適しているようです。どちらも1年という期間の移動平均線でほぼ同じものです。
大きな流れを見るために、月足で20年間の日経平均の動きを下に掲げました。添えられている線は12カ月移動平均線です。
 【図3】日経平均チャート(日足)*楽天証券マーケットスピードより
【図3】日経平均チャート(日足)*楽天証券マーケットスピードより
これを見ると12カ月移動平均線(≒52週移動平均線)が、日経平均のトレンドやサイクルをよく表していることがわかります。
大雑把にいえば、
・12カ月移動平均線(≒52週移動平均線)が上向いている時……儲かりやすい
・12カ月移動平均線(≒52週移動平均線)が下向いている時……儲かりづらい
ということがいえると思います。
ですから、「12カ月移動平均線ないし52週移動平均線が上向きになってきたところが、絶好の株の投資ポイントになる」ということが、経験上言えます。
しかし、12カ月移動平均線が上向いたポイントと言っても、上のチャートのD地点のように上昇トレンドのごく初期段階のこともあれば、C地点のようにほとんど上昇トレンドの終了近くになってしまうケースもあります。
できればD地点のように上昇トレンドの初期段階を捉えたいものですが、そのためにはどういうことに注目したらいいのでしょうか。
上昇トレンドの初期段階を捉えるための移動平均線を見るコツ
先ほどのC地点とD地点について少し詳しく見るために、下に両地点の週足チャートを掲げました。
週足チャートですから、12カ月移動平均線ではなくて、それにほぼ相当する52週移動平均線を表示し、さらに13週移動平均線と26週移動平均線も表示しています。2つのチャートにどんな違いがあるのか、見比べてください。
 【図4】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
【図4】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
 【図5】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
【図5】日経平均チャート(週足)*楽天証券マーケットスピードより
見比べていかがでしょうか。違いは一目瞭然だと思いますが、その違いは、
・C地点のチャート・・・移動平均線と株価がバラけている
・B地点のチャート・・・移動平均線と株価が収れんしている
ということです。
株価の横ばいの調整が続くと、株価と移動平均線が収れんするという形になります。とくに、Dのように、13週、26週、52週の各移動平均線と株価が全て収れんする形になって、そこから上昇し始めるのは最高の買いサインになることが多いです。このパターンでは、全ての移動平均線が一斉に上向き、株価も全ての移動平均線の上に位置する形になります。つまり、線の向きや株価の位置など、「全ての買いサインが一斉点灯する形」になるのです。
なお、C地点のチャートでは、C地点より少し前のC’地点で、13週移動平均線と26週移動平均線がほぼ同時に上向き、株価もこの両線を上抜いているので、なかなか良い買いサインのパターンになっているといえます。52週移動平均線はまだ下向いているので、この買いサインは“だまし”になる可能性もあり、その点がやや不安ですが、その後上昇が続き52週移動平均線も上向く形になりました。
しかし、上昇トレンドが開始してからC’地点、C地点の買いサインまではタイムラグが結構ありましたし、上昇もある程度進んでしまっていました。それと比較すると、全ての買いサインが一斉点灯したD地点のパターンはかなり優れた買いパターンといえるでしょう。
さて、最後に14年7月初旬現在の日経平均状況ですが、52週移動平均線はまだ上向いていますので、そうした点ではアベノミクス相場はまだ終わっていないと言えるでしょう。
しかし、26週移動平均線が下向いてきていて、これが上昇トレンド終了の前兆にもなりうるので、この点は気になるところです。26週移動平均線が一段と下向き、52週移動平均線まで下向いてくると、株価トレンドが転換する可能性が高まるので、今後はそうした点に注意しながら相場を観察していくといいのではないかと思います。
◆27万部突破の大ベストセラーがリニューアルして帰ってきた!
この本は、1日1章ずつ、7日間読むことで株価チャートの基礎から応用とデイトレやウィークリー・トレード、信用取引のやり方がわかるようにできています。全ページカラーで大きくわかりやすい図解がメイン。ほとんどすべてのパターン、手法について事例をあげて詳しく解説していますので本書で得た知識をすぐに実践で役立てることができます。
【本書でできること】
1.株価チャートの知識を基礎から応用まで一気に学べる
(ローソク足ってなに?から、テクニカル指標までをこの一冊で)
2.学んだ知識を実践で役立てられるよう、豊富な事例を紹介(事例はすべて最新のもの)
3.さらにセミプロ級になるためのテクニックを公開 (例)・短期トレード&デイトレのやり方&詳細テクニック集/信用取引の活用法/マーケットスピードのマニュアル…など
【本書の7大特徴】
・全ページカラーで見やすい!
・大きな図解でわかりやすい!
・やさしい文章で初心者フレンドリー!
・豊富な事例で実践的!
・「売り」(損切り・利益確定)のタイミングを1章まるごと割いて解説!
・詳しい「用語解説」付き!
・マーケットスピードの使い方もわかる!
⇒楽天ブックスで購入はコチラから
⇒電子書籍・koboでの 購入はコチラから
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月16日時点・最新情報】
|
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード(NL) |
||||
| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |
||||
◆JCB CARD W(ダブル) |
||||
| 1.0~10.5% (※1) |
永年無料 | JCB | QUICPay |
 |
| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |
||||
◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
||||
| 0.3~1.5% (※1) |
3万9600円 | AMEX | - |
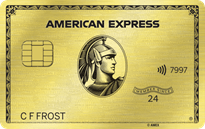 |
| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |
||||
| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード ゴールド(NL) |
||||
|
0.5~7.0% |
5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |
VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |
||||
◆三菱UFJカード |
||||
| 0.5~7.0% (※1) |
永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
- |
 |
| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |
||||
◆楽天カード |
||||
| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |
 |
| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |
||||
| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |
||||