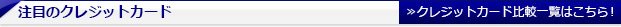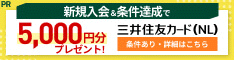上昇するスマホ代に対し、支出の総額は減少……
家計に占めるスマホ代の割合が増加中!
家計のなかで「通信費」の増加に悩んでいる人は、大変多いようです。通信費の大半を占めるのは、言うまでもなくスマホ・携帯電話料金です。ご存じのように、今はスマホ全盛の時代。通信・通話だけでなく、スマホで動画を見たり、ゲームアプリを利用したりして、データ通信量を多く使用する人が増えました。そのため、必然的にスマホにかかる料金も高くなっているわけです。
下図は、ここ10年ほどの平均的な年間の固定電話代と移動電話(スマホ・携帯電話)代の推移をまとめたものです。図版の一番下の段は、1年で使ったお金の合計金額の平均値です。これを見ると、固定電話の料金が減って、スマホ・携帯電話の料金が増加しているのは一目瞭然です。さらに、家計全体の支出は徐々に縮小化しているため、家計に占めるスマホ・携帯電話の料金の割合が、かなり高くなってきていることがわかります。
| ■「通信費」の推移と「通信費が世帯支出に占める割合」の推移 | ||||||||
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ||
| 通信料 | 合計 | 11万 971円 |
11万 1404円 |
11万 771円 |
11万 1371円 |
11万 11906円 |
11万 2453円 |
11万 3775円 |
| (うち固定) | 3万 3212円 |
3万 1418円 |
3万 853円 |
3万 806円 |
3万 429円 |
2万 9354円 |
2万 7536円 |
|
| (うち携帯) | 7万 7759円 |
7万 9986円 |
7万 9918円 |
8万 565円 |
8万 1477円 |
8万 3099円 |
8万 6239円 |
|
| 通信料が 世帯支出に 占める割合 |
2.48% | 2.63% | 2.64% | 2.72% | 2.74% | 2.75% | 2.86% | |
| ※出所:総務省「家計調査」(総世帯) | ||||||||
この統計の直近のデータを見ると、スマホ・携帯電話料金の平均は月7000円程度ということになります。しかし、これは「総世帯」のデータであり、実は「勤労者世帯」に限定したデータを見ると、スマホ・携帯電話料金の平均は月1万円ほどまで跳ね上がります。これは、高齢者だけの世帯だと、スマホの利用者が少ないことが原因だと考えられます。
それでも、2人以上の世帯でスマホ・携帯電話料金が月1万円程度に収まっているなら、それほど高いほうとは言えないかもしれません。というのも、今や「4人家族で全員がスマホを持っていて、月々4万円近く利用料がかかっている」というような話も、よく耳にするからです。
確かに、毎月スマホ代が3万円も4万円もかかっていたとしたら、それは家計にとって大きな痛手でしょう。にもかかわらず、「安くするのは難しそう」と、最初から諦めている人も多いかもしれません。しかし実際は、プランの見直しなどで料金の引き下げは可能です。
これは保険とよく似ています。今は、保険料の安いダイレクト保険の普及などで、保険の見直しを意識する人が増えていますが、少し前までは保険会社の営業マンに言われるがまま保険に加入し、毎月何万円も保険料を負担している人が少なくありませんでした。
そのような人は、たいていハイスペックすぎる保険に加入し、保障を過剰につけているのが共通点でした。が、実際にはそこまで分厚い保障は不要なことがほとんどですから、見直しによって保障内容を薄くすることで、保険料を安くすることができたのです。
スマホ代に関しても同じことが言えると思います。たしかに、docomoやau、ソフトバンクといった従来の大手キャリアが提供するサービスは充実しています。契約すればメールアドレスをもらえますし、自分で設定をする手間もありませんし、通話も通信もスムーズにできます。トラブルが発生したら店頭でサポートしてもらうことも可能です。しかし、その分、料金は高くなっているわけです。
まずは「格安SIM」のメリット・デメリットを知って
自分の使い方に合うかどうかを検討してみよう
スマホは使いたいけれど、そんなにサービスが充実していなくても、最低限使えればいいという人は、実は多いはずです。また、今のスマホの機能を自分はそこまで使いこなせていないという人も、きっといるのではないでしょうか?
その場合、スペックのレベルは多少ダウンするものの、利用料金はかなり安くなる「格安SIM」を選択するといいでしょう。
「格安SIM」とは、”SIMカードを差し替えることで低価格で利用可能になる通信サービス”のこと。SIMカードとは、スマホやタブレットなどのモバイル端末で、データ通信や音声通話などを行うのに必要なICチップカードです。大手キャリアのスマホを所有している場合、スマホの中にはそのキャリアのSIMカードが入っています。
「格安SIM」を選択するには、今のキャリアから「格安SIM」を提供しているキャリアに乗り換えて、別のSIMカードに入れ替える手続きをする必要があります。手続きに関しては後で説明しますが、完了すると、スマホ料金をあっという間に1カ月1000~2000円台まで抑えることも可能になるのです。
「格安SIM」に関する噂にはよく聞くし、そこまで安くなるならやってみたい――という人も多いでしょう。しかし、「何だか難しそうだし、不安」と思う人も、それ以上に多いかもしれません。
そこで、ここからは「格安SIM」をさらによく知るために、「格安SIM」のメリットとデメリットを簡単にまとめてみます。なるべく専門用語は避け、わかりやすさ重視でざっくり説明してみました。
【格安SIMのメリット】
◆料金がかなり安く、データ専用で月額1000円以下、音声通話SIMでも月額1000~2000円台に抑えられる可能性も高い
◆ネットや通話のつながりやすさや、カバーエリアは、ほぼ従来の携帯キャリアと変わらない場合が多い(docomoやauの回線を利用している「格安SIM」提供会社が多いため)
◆元の電話番号を引き継げる(MNP)
【格安SIMのデメリット】
◆SMSは使えるがキャリアメールが使えなくなる(「~@docomo.ne.jp」「~@ezweb.ne.jp」「~@softbank.ne.jp」など)
◆今持っているスマホで「格安SIM」に乗り換えられることが多いが、利用しているキャリアや端末によってはNGなので、その場合は新たにスマホを買う料金が発生する
◆長時間通話すると、かえって割高になる可能性があるため、仕事などでよく電話をする人には不向き
◆格安SIMカードが届くまで、数日間スマホが使えなくなる場合がある
「格安SIM」最大のメリットは、前述のように使用料が格段に安いところです。それでいて、ネットや通話のつながりやすさにも問題がありません。なぜなら、回線はdocomoやauといった大手キャリアが提供しているからです。多少通信速度が遅くなることはあるといわれますが、「格安SIM」にしたことを後悔するほどひどくはないようです(移動中も動画を見るなど、インターネットヘビーユーザーかどうかで、感想がわかれることもあります)。
しかも、電話番号を変えずに乗り換えられます。端末さえ買わないで済む場合も多く、元のスマホに「格安SIM」のカードを差し込めばそのまま使えるのも便利です(購入しなければならないこともあります)。
キャリアメールのアドレスは消えてしまうので注意。
「無料通話」がないので「格安SIM」での長電話は控えよう
反面で、より気がかりなのはデメリットの部分でしょう。
まず、キャリアメールが使えなくなる点は要注意です。「LINE」や「gmail」「SMS」をおもに利用するようにすれば、なくてもそれほど困らないかもしれません。ですが、キャリアメールでしかつながっていない友人・知人などとは、関係が途切れる可能性があります。
また、スマホの買い替えが必要な場合、「格安SIM」の初期手数料(おおむね3000円程度の場合が多いようです)のほか、スマホ代として安くても1万~3万円かかってしまうのが痛いかもしれません。
さらに問題は通話料金です。「格安SIM」の場合、大抵30秒で20円の通話料金になります。これは、docomoなど大手キャリアのスマホと同等なのですが、大手キャリアのスマホとは違って、「格安SIM」には無料通話分がありません。
ということは、ついうっかり話し込んで1時間経過してしまった場合、いきなり2400円もかかることになります。よって、わりと長電話もしたい人、仕事でよく電話する人などには、あまり「格安SIM」は向いていないと言えます(SMS受信ができる格安SIMを利用する場合には、次のページで紹介する「LINE Out」を利用することでも通話料を抑えることができます)。
最後に、一過性の問題ではありますが、電話が数日不通になってしまうのも、困らされる部分です。店頭で手続きをした場合などは、即日使えることもありますが、多くの場合は新しいキャリアでMNP(前と同じ電話番号を引き継ぐこと)の転入手続をした時点で、元の契約が解約されます。
大手キャリアから大手キャリアに転入するときには、手続きは即時実行されるため、電話の不通期間が生じることはまずありません。しかし、「格安SIM」のキャリアに転入するときには、手続きに数日かかるのも普通です。
元の契約が解約され、「格安SIM」の手続きに時間がかかっている間は、電話が不通になり、メールもLINEも使えません。よって、事前に連絡をしておかないと「音信不通」と思われてしまいます。メールやLINEを自宅のパソコンでも使えるようにしておくなど、対処法を考えるべきでしょう。
「ゲームアプリ」は意外と通信量が少ないものが多い。
曲のダウンロードの通信量は多いので要注意
さて、ここまで「格安SIM」のメリット、デメリットを比較してみて、どうでしょう?
恐らく、大半の人は「格安SIM」を使うメリットのほうがデメリットを上回っているのではないでしょうか。スマホを仕事で使う人を除いて、最近はおもにLINEで連絡をとる人が増えているので、通話はあまり使わず、通信がそこそこできればOK――という利用者のほうが多いはずです。それならば、「格安SIM」で問題ありません。
では、人気のゲームや音楽を楽しむ場合はどうでしょうか?
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月16日時点・最新情報】
|
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード(NL) |
||||
| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |
||||
◆JCB CARD W(ダブル) |
||||
| 1.0~10.5% (※1) |
永年無料 | JCB | QUICPay |
 |
| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |
||||
◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
||||
| 0.3~1.5% (※1) |
3万9600円 | AMEX | - |
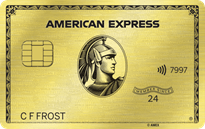 |
| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |
||||
| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード ゴールド(NL) |
||||
|
0.5~7.0% |
5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |
VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |
||||
◆三菱UFJカード |
||||
| 0.5~7.0% (※1) |
永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
- |
 |
| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |
||||
◆楽天カード |
||||
| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |
 |
| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |
||||
| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |
||||