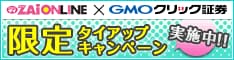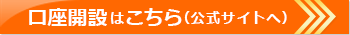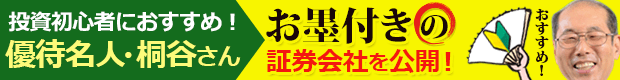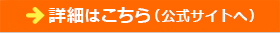こんにちは、個人投資家の立川です。
前回は、投資した元本を配当で回収する戦略を採用しても、「可能であれば最初は再投資して、あとから元本を回収したほうが効率がいい」という話をさせていただきました。
【※前回の記事はこちら!】
⇒「配当金」を再投資すれば、複利効果によって配当金&資産増加のスピードが加速する!「増配株投資」の優位性をさらに高める「配当金」の使い道を伝授!
さて、増配株投資といえども、投資対象は生身(?)の会社。企業は人が運営していますから、投資している増配株の業績が常に好調であり続けるとは限りません。突然、社員の不祥事や業績の下方修正などのネガティブなニュースが発表されることもあります。そこで今回は、投資先にネガティブなニュースが流れたとき、増配株投資を実践する投資家はどのように対処したらいいのかを考えてみましょう。
業績の下方修正、減収減益、減配、無配転落……etc.
保有銘柄のネガティブなニュースにどう対応するか?
今年3月のことですが、私が10年以上保有していた「プロトコーポレーション(4298)」を配当の権利付き最終売買日の前に売却しました。2005年に初めてプロトコーポレーションを購入して以来、買い増しはしたことがありましたが、売ったことはありませんでした。プロトコーポレーションは連続増配ではなかったものの増配傾向にあり、保有期間だけでも配当は6倍になっていました。2001年からプロトコーポレーションを保有していた人は、配当が8倍になっているほど増配していた銘柄でした。
| ■プロトコーポレーション(4298)の配当金の推移 | ||||||||
| 基準月 | 2002年 3月 |
2003年 3月 |
2004年 3月 |
2005年 3月 |
2006年 3月 |
2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
| 配当金額 (税引前) |
6.25円 | 8.33円 | 8.33円 | 8.33円 | 8.33円 | 13.33円 | 25.00円 | 35.00円 |
| 基準月 | 2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
| 配当金額 (税引前) |
35.00円 | 37.50円 | 42.50円 | 37.05円 | 37.50円 | 38.00円 | 39.00円 | 50.00円 |
| ※株式分割考慮後の配当金額 | ||||||||
しかし、これだけ増配してきたプロトコーポレーションですが、過去には大きな下方修正を3回しています。
[2011年3月11日]
純利益(予想)40.56億円⇒(修正)29.38億円(一株利益280.90円 > 配当75.00円)
[2015年4月17日]
純利益(予想)34.40億円⇒(修正)24.10億円(一株利益118.01円 > 配当38.00円)
[2018年3月23日]
純利益(予想)21.20億円⇒(修正)6.60億円(一株利益30.24円 < 配当50.00円)
ところが、何度も下方修正を出しながらも増配傾向にあり、株価もここ数年は1200~2000円のレンジ内で推移していました。過去の下方修正は利益が会社予想に比べて減少はしたものの、増配傾向にあったために特に売却を考えたことはありませんでした。
プロトコーポレーションは、ざっくり言うと中古車情報を加工して売るのが仕事ですが、情報の仕入れの段階でお金を受け取り、情報を販売しても受け取るという一粒で二度美味しい商売をしていたため、中古車以外にも領域を広げていくことで、将来的には売上も利益も伸びていくと考えたためです。また、プロトコーポレーションは配当も一株利益の3分の1以下で、今後の増配も十分に余裕のある状態でした。
しかし、事業拡大のための買収がことごとく失敗したプロトコーポレーションは、2018年3月期に減損損失を計上することになり、その結果として、一株利益が予想配当を下回ってしまいました。かつ、プロトコーポレーションはここ数年、売上は拡大していたものの、利益は減少傾向にあった中で、ついに純利益の予想が大きく下方修正されることになったのです。
「減損損失の発生」や「業績の下方修正」が発表されたのは2018年3月23日で、私はその時点で、プロトコーポレーションが今後、さらに増配を続けていくことに疑いを持ち、迷わずに保有していた株の大部分を翌日に売却し、しばらくして残りの保有株もすべて売却しました。幸い、買値から3倍程度の株価で売却でき、かつ、その間の配当も受け取っていたので、損をすることはありませんでした。その後、プロトコーポレーションは2019年3月期には業績が大きく回復するという会社予想を出しましたが、私はこの予想を信じることができなかったために買い戻しはせず、そのままになっています。
増配株投資で売却するかどうかの目安は
「一株利益 < 配当」となるか「減配」するか
プロトコーポレーションはバリバリの増配銘柄で、しかも私の場合はあと少しで投資元本を配当で回収できていたので、業績が悪化しても、保有し続けて配当を受け取るのも選択肢の一つだったと思います。というのも、「仮にネガティブなニュースが出て、保有に不安があれば売却するのも選択肢の一つだが、増配株への投資であれば保有を継続したとしても損失は小さく済む」からです。
しかし、私の場合は業績が悪化して赤字になったり、長期的に業績の低迷が継続しそうになったりすると売ることにしています。特に、増配の継続が難しそうなときには売却します。その後、業績を回復させて増配基調に戻るかもしれませんし、株価も上昇するかもしれません。実際に、増配を再開したり、株価が上がったりして悔しい思いをしたことがいくらでもあります。しかし、増配株はほかにいくらでもありますし、不安を感じながら保有するくらいであれば、一旦売却して別の銘柄に投資するか、再び増配傾向に回復するのを待って投資し直したほうが精神衛生上いいと考えています。
実際、先ほどのプロトコーポレーションを例にとっても、保有していた期間に2回あった下方修正後は株価が横ばいで推移した期間が長かった印象です。下方修正を発表したときに売って、ほかの銘柄に乗り換えていたほうが株価も上がっていたようですし、増配率も高かったようなので、私のポートフォリオ全体のパフォーマンスはよくなっただろうと思います。これは私の投資家人生の中でも大きな反省点でもあります。
とはいえ、保有している銘柄を買った株価よりも安い株価で売却するのは非常に難しいものです。以前は私も「株価がせめて買値に戻るまでは……」と躊躇していました。しかし、一時的に損失を出しても「買い替えた銘柄で取り返せばいい」と考えるようになってからは、判断に迷ったり、保有に値しないと考えたりしたら、すぐに売却できるようになりました。結局、保有するか、売却するか迷うような銘柄は、結局はその後もズルズルと株価を下げるケースが多いですし、もし、売却後に保有していても問題がなかったと思い直せば、そのタイミングで買い戻せばいいのです。
私は「売却するかどうかの目安」として、「一株利益 < 配当」となるか、もしくは「減配」となったら、その銘柄の売却を検討することにしています。「一株利益 < 配当」となると、将来的には「減配」する可能性が高くなります。そして、いよいよ「減配」となったら「増配株に投資して、配当で投資元本を回収する」という「増配株投資」の前提が崩れるので、保有する理由がなくなります。
あとは、その銘柄を信じられるかどうかで、その銘柄のことを信じられなければ売るだけです。「売る=失敗を認める」ことを過剰に恐れて躊躇するのが最悪です。どんなに敏腕なファンドマネジャーであっても、投資する銘柄選択に失敗することなんていくらでもあります。私のようなサラリーマンの兼業投資家が失敗を失敗と認めなければ、それは傷口を広げるだけです。
増配株投資は「うまくいかなかった」場合でも
損失が小さくて済むのが最大のメリット!
一方で、多くの銘柄に分散投資をしている場合は、その1銘柄がポートフォリオ全体の成績や受取配当金に与える影響は小さくなるので、保有し続けるという考え方もあります。複数の増配株に分散投資をしていれば、配当で投資元本を回収するためにかかる期間は1~2銘柄が倒産したとしても大きくは変わらないので、保有しながら業績の回復を待つこともできるでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒増配株への分散投資は、預貯金よりもリスクが低い? 配当金だけで投資元本を回収できる期間が短くなり、元本回収後はリスクフリーで高い配当金がもらえる!
そもそも増配株は倒産しにくいビジネスモデルを持っているからこそ増配できるのです。ネガティブなニュースが流れたとしても、その企業の業績の回復を信じることができれば、保有を継続するのも「あり」でしょう。増配株に投資対象を絞って分散投資をしていた場合は、たとえ鳴かず飛ばずの銘柄がポートフォリオに発生しても、その他の銘柄が補って余りあるフォローをしてくれる可能性が高いので、その影響はわずかで済むのです。
株式投資で失敗してしまうと、投資資金を半減させてしまったり、酷いときにはすべてを失ってしまったりすることもあります。しかし、増配株に分散投資する「増配株投資」では、投資をやめなければならないほどの致命傷を負うようなリスクをかなり減らすことができます。「うまくいかなかった」場合でも「被害がかなり小さくて済む」のが増配株投資の最大のメリットなのです。
ちなみに、私が今年の3月に売却してしまったプロトコーポレーションですが、私は売却した時点でプロトコーポレーションという会社に疑いを持ってしまい、結局その後も買い戻すことができませんでした。しかし、今期に入ってからの業績は好調のようで、9月には2019年3月期の第2四半期の業績予想を上方修正して、最近は株価も見直されつつあります。もしかして、売却せずに保有を継続していても問題はなかったかも……と思わずにはいられない、ちょっと残念なことになっています。しかし、その後に少しずつ買い進めたほかの増配株の株価がそれなりに上昇しており、トータルでは悪くない結果になっています。
株価が下落した場合の「損切りライン」は必要なし。
ただし、仕事や生活に影響が出るなら売却して仕切り直そう!
さて、「業績の下方修正」などのネガティブなニュースが出ていなくても、なぜか保有銘柄の株価が下落する、あるいは株式市場全体の軟調な動きに巻き込まれて株価が下落するということがあります。その場合、例えば「買値から10%下がったら」というように、株価が一定のラインまで下がったら売却する、いわゆる「損切り」が頭をよぎる人もいるでしょう。私もあまり株価は気にしないはずの増配株投資を心掛けているのですが、同時に資産も増やしたいという邪(よこしま)な考えを持っているので、保有銘柄の株価下落が続くと「何か自分が知らないネガティブな情報が漏れているのではないか?」と不安になることもあります。
しかし、私は「株価が下落したから」という理由で「損切り」をしたことはありません。といのは、やはり業績を頼りに投資をして、その後の配当をあてにしているからです。株価が上がれば利益を確定する、という売買をしているわけではないんです。ただし、これが正解とは言い切れません。なぜなら、株価下落の背景として、大口の投資家が上場会社のネガティブな面を先に見抜いていたり、先に情報を入手して売り抜けていたりする場合もあるからです。
究極の結論としては、保有している銘柄の株価下落が、あなたの仕事や生活に影響を及ぼすほどの「動揺」をもたらすようでしたら、いったん株を売却してスッキリしたほうがいいでしょう。株は売却したとしてもいつでも買い戻すことができますが、株価が下落する株を保有し続けて落ち着かない日々を過ごしてしまうと、その時間はもう取り戻すことができないからです。「動揺」をもたらすほど株価が下落した場合には、株をいったん売却して頭を冷やし、その銘柄への投資が本当に妥当だったのか、冷静な目で検討してみましょう。
それでは、今回のまとめです。
【ポイント①】
増配株投資の場合、売却するかどうかの目安は「一株利益 < 配当」となるか、「減配」もしくは「増配が期待できなくなった」時点で売却を検討しよう!
【ポイント②】
複数の増配株に分散投資している場合、1銘柄当たりの影響は少ないので、業績が一時的に悪くなっても会社を信用できるなら保有継続も一つの手。
【ポイント③】
「上手く行かなかった」場合でも「損失が小さくて済む」のが増配株投資のメリット!
【ポイント④】
株価が下落して仕事や生活に影響が出るほど「動揺」するようなら、株をいったん売却して、頭を冷やして再度検討するのもおすすめ!
さて、今回は最後に私が注目している増配株を一つ取り上げてみましょう。
現在、EV(Electric Vehicle=電気自動車)化、自動運転など、自動車にまつわるテクノロジーは大きく変化する過程にあります。しかし、どんな自動車も「タイヤ」がないと道を走ることはできません。しかも、自動車が走ると「タイヤ」は消耗するので、世の中に自動車がある限り、「タイヤ」は売れ続けます。そこで注目しているのが「ブリヂストン(5108)」です。ブリヂストンは増配株で、過去20年間で配当は10倍以上に増えており、配当利回りも3%台と比較的高くなっています。
| ■ブリヂストン(5108)の配当金の推移 | ||||||||||
| 基準月 | 1999年 12月 |
2000年 12月 |
2001年 12月 |
2002年 12月 |
2003年 12月 |
2004年 12月 |
2005年 12月 |
2006年 12月 |
2007年 12月 |
2008年 12月 |
| 配当金額 (税引前) |
14円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 19円 | 24円 | 24円 | 26円 | 24円 |
| 基準月 | 2009年 12月 |
2010年 12月 |
2011年 12月 |
2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
| 配当金額 (税引前) |
16円 | 20円 | 22円 | 32円 | 57円 | 100円 | 130円 | 140円 | 150円 |
160円 (予定) |
| ※株式分割考慮後の配当金額 | ||||||||||
仕事の同僚には「いまどき高級なタイヤなんて売れないですよ!」と言われたのですが、ブリヂストンは売上も利益も伸びていて、自動車が便利に進化すれば、さらなる成長が期待できるのでは、と考えています。
さて、第11回で紹介した「インフラファンド」を覚えていらっしゃいますでしょうか?「インフラファンド」とは、太陽光発電施設などの「インフラ」を保有し、そこから得られる収益を投資家に分配する「J-REIT」によく似たファンドです。
【※関連記事はこちら!】
⇒インフラファンドのメリット・デメリットを解説!「J-REIT」と比較しても、「インフラファンド」には高利回り+安定度、不況に強いなど、メリット多数!
しかし、最近になって九州電力が太陽光発電設備に対して出力抑制を実施したり、数年内に太陽光で発電した電力の買い取り価格が半分に引き下げられる方針が決まったりと、「インフラファンド」にとってはネガティブなニュースが流れており、株価も軟調に推移しています。そこで、次回は逆風が吹く「インフラファンド」の未来について、改めて考えてみたいと思います。
【※連載第16回はこちら!】
⇒インフラファンドが抱える「出力制御」「自然災害」「売電価格の低下」という“3つのリスク”を解説!投資対象としてのインフラファンドに未来はあるか?
■立川さんが利用している証券会社はGMOクリック証券とSBI証券!
⇒GMOクリック証券の詳細(公式サイト)を見る
⇒SBI証券の詳細(公式サイト)を見る
| ◆GMOクリック証券 【証券情報⇒GMOクリック証券の紹介ページ】 | |||
| 株式売買手数料(税抜) | 詳細情報(公式サイトへ) | ||
| 10万円 | 30万円 | 50万円 | |
| 88円 | 241円 | 241円 | |
| 【GMOクリック証券のメリット】 ネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用中。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |
|||
| 【GMOクリック証券の関連記事】 ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介!NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは? グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大231回分」の売買手数料が0円に! |
|||
【※立川さんが登場する記事はこちら!】
⇒「連続増配の株を買う」だけで資産1億円超を達成! サラリーマン投資家・立川一さんが編み出したシンプル&ユニークな「増配銘柄投資法」を解説!
⇒株の配当金で暮らす生活も実現可能な投資術を公開! 株の配当が増え続ける会社を選んで投資するだけで、1億5000万円の資産を築いた会社員の投資法を紹介
個人投資家・立川 一(たちかわ はじめ)さん
(『Value Investment since 2004 長期に配当収入増加と資産形成を目指す立川一の投資日記』:https://vis2004.blog.fc2.com/)
40代のサラリーマン投資家。中学生のころから株に興味を持ち、2004年から本格的に株式投資を開始。バフェットの本に影響を受け、最初はバリュー投資からスタートしたが、次第に増配株のメリットに気がつき、現在の投資手法を確立する。趣味である楽器演奏の腕前はかなりのもので、週末にはライブ活動も行っているとか。
■「『夢の配当金生活』実現メソッド」バックナンバー
【第1回】
⇒年収500万円以下のサラリーマンが、投資歴13年で資産1億5000万円、年間配当収入300万円を実現!成功のカギは「増配銘柄への投資」を発見したこと!
【第2回】
⇒定期預金の金利より「株の配当」は数百倍もお得!増配銘柄を選べば、自動的に株価下落リスクが低く、優れたビジネスモデルの超優秀な銘柄に投資できる!
【第3回】
⇒増配株は「元本が増える銀行預金」「部屋数が増えるアパート」のようなもの! 追加投資をしなくても配当が増え、価値も上がる「増配株」のスゴさとは?
【第4回】
⇒増配株への分散投資は、預貯金よりもリスクが低い?配当金だけで投資元本を回収できる期間が短くなり、元本回収後はリスクフリーで高い配当金がもらえる!
【第5回】
⇒「株主優待」の有効活用は「配当金生活」への近道!配当だけでなく株主優待にも注目すれば、投資元本は15年以内で回収できて、リスク管理がパワーアップ!
【第6回】
⇒増配株に投資する際に参考にすべき「指標」とは?割安・割高の目安になる「PER」、資本効率の良さを表す「ROE」「ROA」など「指標」の使い方を解説!
【第7回】
⇒株式投資を始める前に直面する3つの問題を解決!「時間がない」「リスクを取りたくない」「家族の理解が得られない」という悩みを解決する方法とは?
【第8回】
⇒億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介!NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ
【第9回】
⇒サラリーマンが株式投資する前に準備すべきことは?投資資金とは別に、当面の生活費やiDeCoなどを準備して、株式投資による自分年金作りを始めよう!
【第10回】
⇒高配当な「米国株」や「J-REIT」の魅力を分析!増配株投資で成功した投資家が実践する「米国株」と「J-REIT」を利用した「分散投資」の戦略を公開!
【第11回】
⇒インフラファンドのメリット・デメリットを解説! 「J-REIT」と比較しても、「インフラファンド」には 高利回り+安定度、不況に強いなど、メリット多数!
【第12回】
⇒「配当利回りが高い株」に投資するより重要なのは、 「増配傾向にある株」を選んで投資をし続けること! 実現間近の「配当でモトを取る」途中経過も大公開!
【第13回】
⇒株式投資はそもそも「株の売買で稼ぐ」ことでなく、 「出資に応じた利益の分配=配当を受け取る」もの! サラリーマンに「増配株投資」がおすすめの理由は?
【第14回】
⇒「配当金」を再投資すれば、複利効果によって配当金 &資産増加のスピードが加速する!「増配株投資」の 優位性をさらに高める「配当金」の使い道を伝授!
【第15回】
⇒株式投資に「損切り」は必要なのか? 悪材料が出た 場合の「損切り」の必要性や増配の継続性を判断する 方法など、ネガティブなニュースへの対処法を検証!
【第16回】
⇒インフラファンドが抱える「出力制御」「自然災害」「売電価格の低下」という“3つのリスク”を解説!投資対象としてのインフラファンドに未来はあるか?
【第17回】
⇒個人投資家は「株価暴落」にどう対応すべきなのか?株価の急変に右往左往しないためには「株価の変動を気にしなくていい投資手法=増配株投資」を選ぶこと
【第18回】
⇒「資産運用」は、40~50代から始めても遅くない!40~50代が定年退職や老後に備えて「増配株投資」で資産運用するメリットと注意点をわかりやすく解説!
【第19回】
⇒配当金生活を実現するなら「日本株」より「米国株」に投資すべき!? 50年以上の連続増配株が約30銘柄もある「米国株」の魅力と注意点をわかりやすく解説!
【第20回】
⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
【第21回】
⇒「株」を買う理由は、本当に“増配”だけでいいのか?何歳までに始めるべきなのか?など、株初心者が抱きがちな「増配株投資」の“3つの疑問”をまとめて解決!
【第22回】
⇒「高配当株」と「増配株」では、どちらに投資すべきか?「増配」は業績やビジネスモデルの“裏付け”があるが、「高配当」は株価や配当額に左右される不安定なもの!
【第23回】
⇒「増配株投資」は“コストパフォーマンス”が高い投資法なのか? 投資に必要な「手間」や「時間」を、「配当金」で回収できるかどうかをシミュレーションして検証!
【第24回】
⇒賢い「お金の貯め方&使い方」を“億超え”サラリーマン投資家が伝授! 若いうちにもっとも重視すべきなのは「経験」でも「節約・貯金」でもなく「株式投資」!
【第25回】
⇒「東証インフラファンド指数」の登場で、インフラファンドの出来高急増&投資口価格の上昇も!? 指数連動型の投資信託の設定や機関投資家の参入に実現に期待!
【第26回】
⇒米国株投資をする際に気になる「為替変動リスク」にどう対応すべきか? 配当生活を目指す個人投資家が考える「為替変動リスク」の捉え方と回避する方法!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
| 【2025年12月2日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |
||||||
| 株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||
| 1約定ごと | 1日定額 | |||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2628本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
| 【SBI証券のおすすめポイント】 口座数では業界トップクラスの大手ネット証券で、最大の魅力のひとつは国内株式の売買手数料が完全無料なこと。取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2025年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で9年連続1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
| ◆三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1857本 | ○ 米国 |
|
| 【三菱UFJ eスマート証券のおすすめポイント】 MUFGグループの一員であり、さらにau経済圏と連携するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査<金融業界編>」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ |
||||||
| ▼【ザイ限定】2000円プレゼントの特典情報も掲載!▼ | ||||||
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1921本 | ○ 米国 |
|
| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。HDI-Japan主催の「HDI格付けベンチマーク」2025年証券業界では、「問合せ窓口」「Webサポート」2部門で3年連続「三つ星」を獲得。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1846本 | ○ 米国、中国 |
|
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、5100銘柄以上の米国株や2650銘柄以上の中国株を売買できる。「dカード」「マネックスカード」などの提携クレカで投資信託を積み立てると最大3.1%のポイント還元。さらに、投資信託の保有金額に対し、最大0.26%分(年率)のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ! ポイント還元率は最大3.1%とトップクラスで、「dカード PLATINUM」ならお得な特典も満載! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆【マネックス証券NISA「つみたて投資枠」のメリットは?】積立対象の投資信託が264本もあり、初心者も安心の資産設計アドバイスツールが使える! |
||||||
| ▼クイズに回答+口座開設で2000円分のポイントがもらえる!▼ | ||||||
| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 660本 | ○ 米国 |
||||
| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国で設立され、グローバルに展開しているネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は約6300銘柄と大手ネット証券を圧倒。米国株の売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(上限は22米ドルで他社と同水準)。さらに為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株の情報も充実しており、米国株投資にチャレンジしたい人には、魅力的な証券会社と言える。また、日本株の売買手数料が完全無料なので、日本株を売買したい人にもおすすめ。取引アプリに搭載された対話型AIの「moomoo AI」も便利。株の基礎知識から市場動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、投資初心者には力強い味方となる。また、多くの先輩投資家たちが書き込みを行う投資掲示板は、株初心者にとって役立つ情報源となるだろう。NISA口座も利用可能。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! 為替手数料無料&約6000銘柄を24時間取引可能で、AIツールも使える“低コスト&充実のサービス”を解説 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |
||||||
| ▼入金1万円以上で「最大10万円相当の人気株」が当たるキャンペーン実施中!▼ | ||||||
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 2611本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード(一般カード/ゴールド/プレミアム/ブラック)で決済すると0.5〜2%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2600本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
| 1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※電話注文を除く |
163本 | ○ (CFD) |
||||
| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 従来から売買手数料の安さがウリだったが、2025年9月からネット取引の場合、国内株式(現物・信用取引)と投資信託の売買手数料が完全無料に! コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の金利については、大手ネット証券よりも低く設定されており、一般信用売りも可能だ! 米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。国内店頭CFDについては、2024年度まで11年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |
||||||
| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介! NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
| ◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 56本 | - | |
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料(0円)なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |
||||||
| ▼積極的に売買する短期トレーダーに人気!▼ | ||||||
| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||
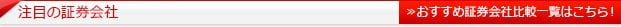
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設+条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら

| お得な限定キャンペーン! | 3000円プレゼント企画! | 株の売買手数料がお得! |
|---|---|---|
|
SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |
岡三オンライン 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ! |
松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |
| ザイ・オンラインで人気NO.1の大手ネット証券!⇒関連記事 | IPOにも注力するネット証券!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |